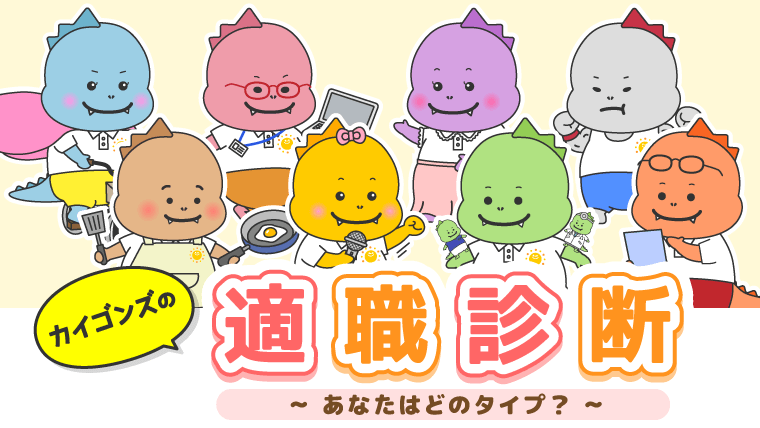第6話「私、変わらなきゃ」
【前回までのあらすじ】
いとこの和子から頼みで伯母の介護を手伝っていた有紀は、いとこ宅に訪れたケアマネジャーとの打ち合わせに同席することに。
第一印象から最悪だったケアマネジャーに対し、内心で不快感をあらわにする有紀。「この人は美佐子おばさんとは絶対にあわない……」と思っていると、案の定、伯母とケアマネジャーが言い争いになってしまう。
相性の悪いケアマネジャーと決裂し、自分達の力だけで美佐子の介護をすると決めた有紀と和子だったが……。
目次
伯母とどう接すればいいか、わからない
私たちの介護は、最初からうまくはいきませんでした。
私が従妹の和ちゃんから頼まれたのは、彼女が雑用で出かける平日の昼間に、伯母の見守りをすることでした。約9時間のうちに食事や排泄の介助もしてほしいと言われました。
料理はそれなりに自信のあった私は、意気揚々と材料を買い込んで家に向かったのですが……
「何も食べたくないわ」
いきなりの拒絶。「おばちゃん、食べないと元気にならないんだよ」と頑張って諭しても、「お腹いっぱいなのよ」と聞く耳持たず。
しかし和ちゃんの残した「介護ノート」には「朝食、半分以上食べず」の文字があるのです。
私がどうしようか悩んでいると、伯母はそそくさと布団をかぶり、「私、寝るから、もう帰ってちょうだい」と言いました。
「大体、なんでゆうちゃんがうちにいるのよ。あなた学校はどうしたの?」
「えっ?学校って、私もうとっくに……」
「……昨日の運動会がいけなかったのね。私、頑張って走りすぎたみたい。おかげで体のあちこちが痛くてクタクタだわ」
伯母は何十年も前の話をしたかと思うと、最後にはありもしない運動会を理由に、目を閉じてしまいました。
何もできない、むなしい9時間
その後も1時間おきに目覚めるのですが、伯母は差し出したお茶も飲みません。リハビリ用にとベッド横に用意したポータブルトイレに誘っても、「大丈夫。さっき一人で行ったから」ととぼけるばかり。これではいけないと思い、意を決しておむつ替えを願い出ると……
「何てことするの!!ゆうちゃんでもやっていいことと悪いことがあるんだからね!」
あの温和だった伯母が、布団に乗せた私の手を叩いたのです。その時に私は、伯母の布団の中が凄まじい便臭で溢れていることに気付きました。
(おばちゃん、うんち漏らしてる!)
伯母さんが便失禁を恥じている。そう思った途端、私はますます伯母にかける言葉を失ってしまいました。そして一度気になると、便臭が鼻にこびりつくように強く感じられました。
結局、腫れ物に触るようにしか接せなかった私は、伯母さんのおむつを替えることはできませんでした。
食事は色々とお伺いを立ててみた結果、ウニとトロの寿司だけは食べてくれることが分かりました。だから私が手伝えたことと言えば、毎日最寄りの回転寿司で買い物するくらいのもの。
おむつ替えもバランスのとれた食事も寝間着の着替えも拒否して眠る伯母の寝顔を、私は毎日9時間、空気清浄機の横からただ眺めて過ごすだけでした。
そんな有り様でしたから、当然、和ちゃんとの関係もギクシャクしてきました。
最初の頃は「お母さんが嫌がることは、無理にさせなくてもいいから」と言ってくれた和ちゃん。
しかし私があまりに何もできないので、日増しに不満を募らせてきたようなのです。いつからか交代の時間にすれ違っても、雑談はおろか目も合わせてくれなくなりました。
私が知らないところで、家族の問題は起きていた
そんなある時、私がいつものように伯母の元に訪れると、遠目からも様子がおかしいのが分かりました。目が真っ赤に腫れていたのです。
「おばちゃん泣いたの?どこか痛いの?」と、私が聞くと
「鬼が大きな鬼が、私のことを叩くのよ」と、めそめそと泣き出しました。
正直、これは伯母との久しぶりの会話でした。私は伯母の世話をするのにとっくに嫌気がさしていて、寝ている彼女をできる限り起こさないようにしていたからです。
だからこの返答に(鬼だなんて馬鹿馬鹿しいことを。またボケが進んだのね)くらいにしか思いませんでした。
――涙を拭うために布団から出てきた、伯母の右手の甲が黒紫に腫れあがっているのを見るまでは。
「おばちゃん!この手、どうしたの!?」
「だから鬼が叩くのよっ、鬼が、鬼が……」
私は事情もよく呑み込めないまま、とにかく伯母の手を冷やしました。そしてこの時初めて、その手が垢にまみれ爪も伸び放題で割れているのを知りました。
次いで恐る恐る布団をめくると、そこには無数の痣がついた細く冷たい素足がありました。ズボンも履かせてもらえず、おむつもパンパンになった状態で。
「ネグレクト」と「虐待」という言葉が頭の中をグルグルと回ります。急に自分が犯罪者になったような気分になって、いてもたってもいられず、私は「おばちゃん、おむつ替えるから!何があっても替えるから!」と怒鳴っていました。
私の気迫に押されたのか、伯母はすんなりとおむつ替えを受け入れてくれました。開いた陰部は痛々しくただれ、排せつ物以外の雑菌で黄緑色に汚れ、見るも無残な状態になっていました。
(おばちゃん、ごめんなさい……!)
虐待の末に、決意したのは……
その夜、私は和ちゃんを正座して待ちました。
「今日、おばちゃんのおむつ替えたの」
「そう……じゃあ、見たんだね」
「うん、見た」
想像と違い、淡々と答えていた和ちゃんでしたが、「何であんなことしたの?」と理由を聞いた瞬間、ぼろぼろと泣き崩れて叫びました。
「ゆうちゃんは何も知らないから、そんなことが言えるのよ!」
この姿と言葉に、私は雷に打たれたようなショックを受けました。
和ちゃんはそれから、ぽつぽつと私の知らない時間の話を始めました。
昼間よく寝ていた伯母は夜になると急に元気になり、歌を歌ったり妄言を繰り返したり、時には家に帰りたいとパニックになることもあったそうです。
中でも和ちゃんが耐えられなかったのは、便失禁をするとすぐにおむつに手を入れて便を外に掻き出してしまうこと。
何度注意しても忘れてしまうので、ついに体で覚えさせようと、失敗するたびに手を叩き足をつねる癖がついてしまったと告白してくれました。
「私だって、お母さんにこんなことしたくないの。でも一晩中眠れないと私だって心も体もボロボロになるのよ。自分の怒りが抑えられなくなるのよ」
私はその時、先日ケアマネジャーと揉めて断ってしまった介護士さんたちを思い出していました。
(介護のプロのあの人たちは、こんな時どうするんだろう……)
私たちは、あまりに介護を知らなすぎた。このままの状態では、きっとまた同じ間違いを繰り返してしまうかもしれない。そう思いました。
すると久しく感じていなかった父の気配が、再び伯母のそばから感じられたのです。
(お父さんが、私に何か言っている気がする……)
認知症のことも何も知らず、父が衰弱しているのも知らず、ずっと疎遠でい続けた私。それを今、今度は伯母で繰り返そうとしていたことに気付きました。
そう思ったら、知らないでいることが途端に悔しくて、恥ずかしくて。
「和ちゃん、私、介護士になるわ」
それが私の口から、ぽろりと出てきた言葉でした。
【つづく】
※この作品は、登場人物のプライバシーに配慮して設定を変えていますが、私が体験した事実に基づいた物語です。